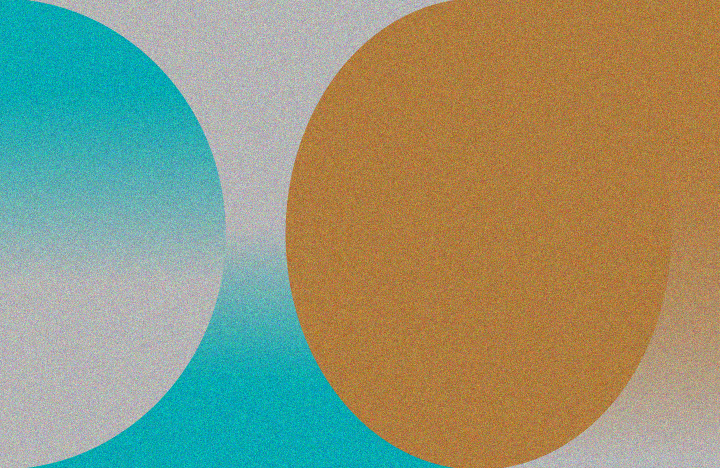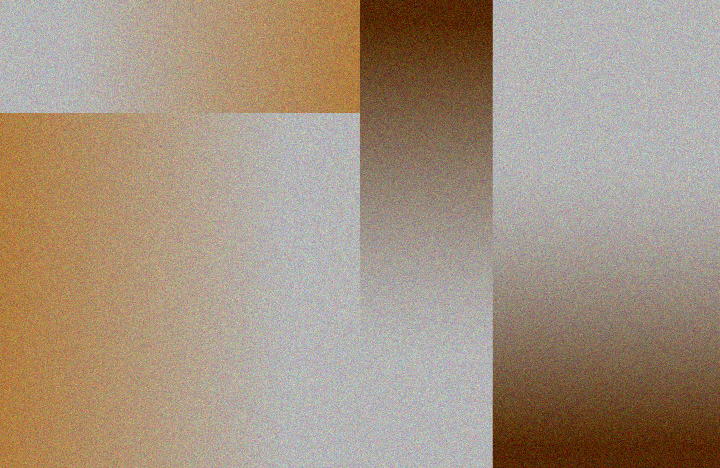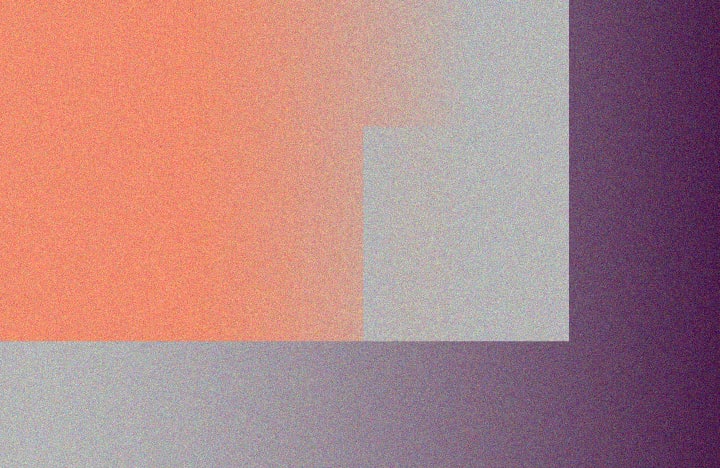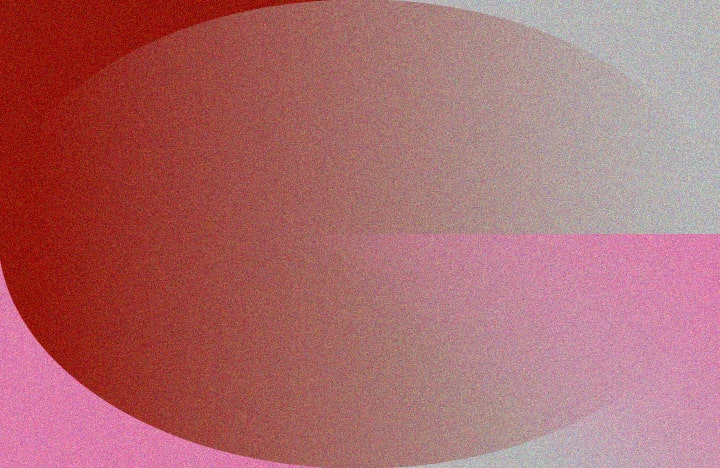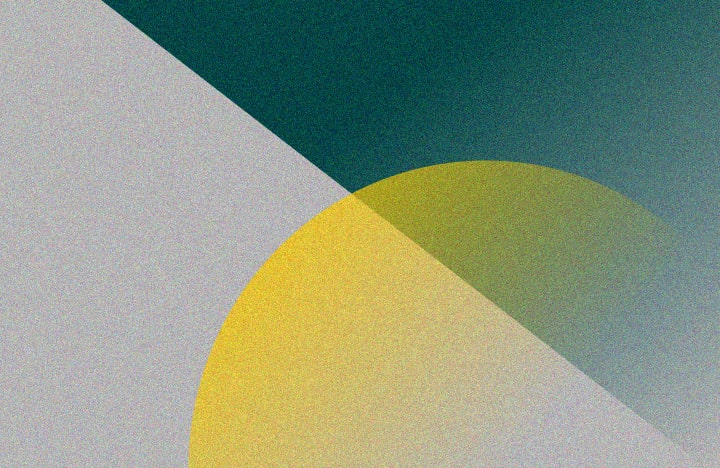Blog
Z世代(1990年代半ば~2010年代序盤生まれ)のライフスタイルが多方面で話題ですが、今回はそうした「世代」による分類のメリットやリスクを改めて考察しました。最後に、世代に対する常識や思い込みにとらわれることなく人物像を把握する方法も紹介します。
ビジネスは想定通りに事が運ぶとは限りません。しかし、たった一言がきっかけで状況が好転する場合もあります。
コピーライターである私はそんな言葉をバタフライエフェクトになぞらえ、「バタフライワード」と呼び、仕事で活用しています。
たとえば、会議に重苦しい空気が流れたとき、プロジェクトが前進しないとき、もっと密度の濃い会話をしたいとき。単なる接続詞でありながら、それ以上の働きをする一言を今回はご紹介します。
目次
Case 01 パーパスがわからない
バタフライワード 【そもそも】
「パーパスを決めたいけど、何から始めればいいんだろう?」「パーパスを仮に決めてみたけど、ホントにこんな当たり前の内容でいいの?」そんな経験はないでしょうか。パーパスとは存在意義。昨今では価値観の多様化、事業の多角化などによりサービスが細分化し、当初の目的を見失いがちです。
そんなときは「そもそも」で原点回帰するのがおすすめ。そもそも目的は何なのか?そもそも何がしたいのか?前へ進むためには時には立ち止まり、振り返るのも悪くありません。
|用例 「そもそも、この事業ってどうして始めたんでしたっけ?」
|Point 周囲から面倒臭い人と思われるのでは?という心配は無用です。皆、誰かが「そもそも」と振り返ってくれるのを待っていたりします。勇気を出して原点に立ち戻りましょう。
Case 02 インサイトが見つからない
バタフライワード 【なぜなら】
インサイトは潜在的なので、顕在化しているニーズに比べ、見つけるのは至難の業。そんなとき「なぜなら」が役立ちます。TOYOTAの生産現場には「5回のWHY」(なぜ?をくり返すことで本質的な問題解決につなげる)という手法がありますが、私はこれをインサイトの発見に応用しています。
たとえば「電動ドリルが欲しい」→「なぜなら」→「壁に穴を開けたいから」→「なぜなら」→「日曜大工で家族に尊敬されたいから」→「なぜなら」→「最近父親の威厳がなくなっているから」といった具合です。くり返すうちに浮かび上がる思わぬ欲求、それがインサイトです。
|用例 「ターゲットは○○○を求めています。なぜなら×××だから。なぜなら・・・」
|Point くり返しすぎると、「結局、人は幸せになりたいから」のように、それ以上深掘りできない哲学的な答えにたどり着いてしまいます。途中で、今までにない発見があれば、そこが「なぜなら」の止めどきです。
Case 03 概念ばかりで話が進まない
バタフライワード 【たとえば】
信頼感、安心感、上質、洗練、ナチュラル・・・。イメージを関係者で共有するのは重要ですが、抽象的な話だけでは、具体的なサービスや商品開発に進めません。先へ進むために有効なのが「たとえば」です。その一言で、半ば強制的に具体案を出さざるを得ない状況に追い込まれます。それはジャストアイデアの企画かもしれません。1枚の参考画像かもしれません。いずれにしても、何もない状態よりもアウトプットの輪郭が見えてきたという意味では前進しています。
|用例 「たとえば、こういう企画なんかどうですか?」
|Point 「たとえば?」と相手に無茶ブリしすぎるのはNGです。あくまでも自分から具体例を出し、抽象的なイメージ共有から具体的な議論へと、場面を転換するきっかけとして使いましょう。
Case 04 バカなフリして本質を突きたい
バタフライワード 【そういえば】
広告の原則に「何を言うか=What」「どう言うか=How」がありますが、関係者同士のコミュニケーションでも同様です。もし相手に落ち度があり事業が渋滞してしまっても、ドヤ顏で指摘しマウントをとるのは賢明ではありません。むしろ逆効果。正論ほど刃は鋭く、相手を傷つけるため、取り扱い(どう言うか=How)には細心の注意が必要です。
そこで便利なのが「そういえば」です。前々から気づいていたり、すでに知っていたりしていても、そのまま伝えずに「そういえば」とオブラートに包むことで、相手の受け取り方は大きく変わります。
|用例 「あ。そういえば、ゴールは認知拡大でしたっけ~?」
|Point 「あ。」が大事です。まるで自分も同じように忘れていたけれど、たった今、思い出したような演技を心がけましょう。こうしてバカなフリを自由自在にできるのが真の賢者です。
Case 05 トライ&エラーしたい
バタフライワード 【とりあえず】
柔軟かつ効率的に、迅速なシステム提供を目指すソフトウェア開発手法「アジャイル」。提唱されたのは2001年アメリカでのことですが、日本にはまだまだ浸透しているとはいえません。日本特有の組織体制や、気軽に挑戦できない企業風土などが要因に挙げられますが、そんな失敗できない環境こそ最大の失敗といえます。
「とりあえず」と聞くと、浅はかで、どこかテキトーな印象を受けるかもしれません。しかし、まずやってみて、ダメなら直す。それをくり返して完成させていくほうが、何もせず悩んでいるよりも、または準備しているうちにタイミングを逃してしまうよりも、ずっと建設的です。
|用例 「とりあえず、やってみますかっ!」
|Point 最初から成功する人はいません。失敗を恐れず軽い気持ちで(失敗しながら成功に近づいていく覚悟で)はじめの一歩を踏み出してみましょう。ノリは大事です。
Case 06 コモディティ化している
バタフライワード 【しかも】
多種多様なモノやコトが溢れる現代、オリジナリティの創出は容易ではありません。差別化が事業の足止めになる例も少なくありません。そんな場合は「しかも」を使いましょう。予想もしないプラスアルファの付加価値が生まれ、差別化できる可能性があります。商品開発、サービス開発の段階で使うのが効果的です。
「しかも」の後に続くのは、元の価値の延長線上の事柄ではなく、まったく異なる事柄を掛け合わせたほうが新しい価値は生まれやすくなります。
|用例 「甘くておいしい。しかもヘルシー(味とは別の事柄)。しかもリーズナブル(健康とは別の事柄)。しかもサステナブル(価格とは別の事柄)」
|Point もし差別化できたとしても、それは単に違いが生まれただけで、必ずしも消費者に望まれているとは限りません。ニーズがないから他社が手を出していないだけかもしれません。本当に求められているかどうかを見極めましょう。
Case 07 状況が複雑化している
バタフライワード 【要するに】
VUCAの時代といわれています。メタバース、NFT、WEB3など新たな概念や言葉も次々と生まれ、世界は複雑化の一途をたどっているといえるでしょう(なかには小難しい言葉ばかり並べ、わざと状況をややこしくしているのでは?と疑いたくなる例もありますが)。
何者かとらえどころがないとき、優先順位がわからないときに、強引に結論づけることができるのが「要するに」です。コピーライターの仲畑貴志氏は「早い話が、という言葉を冒頭につけて考えると自分が言おうとしてることの核心が見えてくる」と語ります。もし「要するに」の後に続く一言に魅力がなければ、そのサービスや商品は再考の必要があるかもしれません。
|用例 「要するに、この商品は世界の食糧不足を解決します!」
|Point 「要するに」はあくまでも一つの結論を導き出すための作業です。その作業中にこぼれ落ちる〝情緒〟や〝遊び〟も案外、サービスや商品に欠かせない要素だったりするので注視しましょう。
Case 08 内なる情熱を引き出したい
バタフライワード 【それでも】
事業を進める際によくあるのは、関係者のさまざまな意見が加わり、せっかくの先鋭的なアイデアが丸くなってしまうこと。また、思わぬ壁にぶつかり、方針転換せざるを得ないこと。そこで折れるのは簡単ですが、粘った先に新しい価値が生まれる場合もあります。そして、その価値を見たいという情熱を、じつは一人ひとりが秘めている場合も。
そんな情熱の原石、荒削りの気持ちは、「それでも」で引き出せます。仕事柄、私はインタビュー取材をよく行いますが、ここぞというときは「それでも」を使っています。ビジネスの現場では、相手が意気消沈しているときや、チームにあきらめムードが漂っているときに発すると効果を発揮するでしょう。きっと、人間臭い欲求や感情が相手から飛び出すはずです。
|用例 「事情はわかりました。それでも続けている原動力はなんですか?」
|Point 空気を読んで、引くときは引きましょう。こちらが期待しているようなドラマチックな回答を、残念ながらすべての人が持っているとは限りません。
Case 09 本音を引き出したい
バタフライワード 【実際】
先ほどご紹介した「それでも」も有効ですが、それによって引き出せるのは、逆境に負けないアツい気持ち。一方「実際」で引き出せるのは、情熱だけでなく、ポジティブもネガティブも含むもっと広範囲な本音です。
ビジネスの現場で本音と建前を使い分けるのは当然ですが、建前ばかりではメンバーの共感を得るのは難しいものです。インターナルコミュニケーションに限らず、消費者コミュニケーションにおいても同様です。昨今ではファンベースマーケティングが重視されていますが、ファンの心をつかむには、飾らない本当の気持ちや透明性も大切です。
|用例 「で、実際、どうなんですか?」
|Point 「ここだけの話」と後に付けるのもおすすめです。相手が「いや、じつは・・・」と切り出した内容に、課題解決のヒントが隠れていることが大いにあります。
Case 10 どうしても伝えたいことがある
バタフライワード 【ちなみに】
一人ひとりにはきちんと考えがあるのに、誰も切り出せないまま会議が終わってしまい、ずっとモヤモヤ。そんなストレスを回避するための一言が「ちなみに」です。一般的に「ちなみに」は補足の意味ですが、ここでは関係ありません。
どうしても伝えたいからといって、血気盛んに話し出せば、聞き手は思わず身構えてしまうでしょう。そうして期待値が上がるのに比例して、期待はずれのリスクも高まります。大切なメッセージほど導入のハードルは下げるのが、相手に聞き入れてもらうコツです。
|用例 「ちなみに、このプロジェクト、絶対に参加したかったんですよ」
|Point 「ちなみに」の後で、一呼吸置くのが上級者のテクニック。伝えたいメッセージが、より際立ちます。なお、ハードルを下げる目的で「わかんないんですけど」を多用する人もいますが、「わからないなら言うなよ」というカウンターを食らう場合もあるので気をつけましょう。
今回ご紹介したバタフライワードは、決して万能ではありません。けれど、第一声で状況に最適なワードを発することによって、それに続く第二声、第三声の発言内容が、事業を動かすうえで意味あるものになる可能性はあります。普段の仕事で使ってみてはいかがでしょうか。とりあえず。
This is New Perspective
「とりあえず」はテキトーじゃない。「それでも」はしつこくない。
たった一言で、停滞していた事業が活性化することもある。

石塚 勢二
COPYWRITER
広告制作会社で多くの企業の広告、プロモーションに携わった後、入社。コピーライティングに限らず大局的な視点に立ち、ブランドのコンセプト開発からコミュニケーション戦略の立案、動画・音声コンテンツの企画・シナリオ設計まで行う。